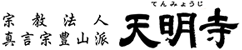-
2025.03.26
なぜツボを買ってしまうのか?
「先祖供養をしないと病気は治らない」「これを買えば不幸から逃れられる」
そんな言葉で人の不安をあおり、高額な壺や数珠、印鑑などを売りつけるいわゆる“霊感商法”が問題になりましたね。
「洗脳されていた」「冷静な判断ができなかった」「うまく丸め込まれた」
不安や孤独に心が傾いたとき、大金を支払ってしまうのです。
お寺で納めていただく「お布施」には、明確な金額の決まりがありません。
基本的には「お気持ちで」とお伝えしており、納める方の想いに委ねられています。とはいえ、最近では地域や内容に応じて、ある程度の目安が示されることもあります。
お布施の額には、「故人への想い」「お経の価値」「住職への感謝」など、さまざまな意味が込められることが多いですが、もうひとつ大切な視点があります。
それは、「自分自身の価値」を見つめるということです。
お布施の根底にあるのは、仏教の「喜捨(きしゃ)」という考え方です。
“寄付”や“献金”とは少し異なり、喜捨とは「自分の善き行いは、巡り巡って自分に返ってくる」という因果の法則に基づく価値観です。
ベンモウが学生時代、お金がなくて先輩にご飯をご馳走になったとき、こんな言葉をかけられたことがあります。
「俺も昔、先輩におごってもらったからな。次はお前が後輩におごってやれよ」
この一言を聞いて、「自分に後輩ができたら、同じようにしよう」と自然と思いました。
それは単なる“恩返し”ではなく、人とのつながりや、いま自分が生きていることへの感謝を、行動で示すということだったのだと、今になって感じています。
亡き人やご先祖さまへの想いを形にするという行為は、実は、自分自身がしっかりと「今」を生きることへとつながっているのです。
「先祖供養が大切だ」と言われる理由は、供養のためだけではありません。
それは、今の自分の生き方を確認し、見つめ直す機会でもあるからです。
では、先祖供養とお寺へのお布施がどのように結びつくのか?
それは、一時的なお付き合いではなく、長期的なお付き合いが前提にあるからこそ、菩提寺と檀家さんとの関係が成り立つのです。
一時の不安に付け込まれないためにも、日頃からお墓参りを心がけ、精神的な支えとなるお寺との関係性を、もっと大切にすることがよいですね
※YouTube更新しました!
『行ってはいけない観光地(お城)』
①HPコラム/人間関係とお金に関する悩み(丸儲け住職YouTube)
②Facebook一般投稿 寺院運営を中心とした経営の話
③Facebook成功する寺院運営(オンライン会員限定)
天明寺の実践的な内容と具体例、ベンモウの考え
④X(ツイッター)毎日の名言・丸儲け住職YouTube内容のまとめ
⑤インスタ 人間関係とお金に関する悩み発信
⑥note 現代のお寺事情