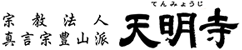-
2025.05.07
気分経営
葬儀や法事におけるお布施については、「金額の提示はすべきではない」という考え方が、今でも寺院業界では常識とされています。
「お布施は商品の売り買いではない。だから金額を示すのはおかしい」というのが、その理由です。
しかしながら、これは現代の感覚とはややズレがあり、「時代錯誤だ」と言われてしまっても仕方がない側面もあります。
お布施の本来の意味について、「高貴な布を差し上げることで、自分の最上の気持ちを表す」といった説明がなされることもありますが、正直なところピンとこない方も多いでしょう。
「なんだそりゃ!」と思われるのも無理はありません。
そこで、語源に注目してみると、少しわかりやすくなります。
お布施は、古代インドの言語であるサンスクリット語では「ダーナー(dāna)」と呼ばれ、それが日本語では「旦那(だんな)」と訳されました。
「旦那さん」という言葉は、「家にお金を運んでくれる人」「食い扶持を支えてくれる人」といった意味から、家の主人や一家の大黒柱を指すようになったのです。
ちなみに、西洋にも「ドナー(donor)」という言葉があります。こちらも「提供する人」を意味し、臓器提供をする人のことを「ドナー」と呼ぶのも同じ語源です。
つまり――
お布施とは「自分の大切なものの一部を差し出すこと」。
それが金銭であれ、物であれ、「施す心」が根底にあるのです。
もちろん、お布施に対する価値観は人それぞれです。
だからこそ、「これが正しい金額です」と一律に決めることは本来できません。
とはいえ、「何も基準がないと困る」という声があるのも、もっともなことです。
そのため、近年では金額の目安をはっきり示しているお寺も増えてきました。
天明寺でも、一定の基準をホームページに掲載しています。
ただし、誤解されがちですが、お布施とは「お経」や「作法」といった“サービスの対価”ではありません。
にもかかわらず、そうした本来の意味が伝わりづらくなっているのが、現代の現実でもあります。
お布施の金額は、ご家庭や個人とお寺との関係性、住職の故人への思い、生前の交流の深さなどによって、自然と変わってくるものです。
そして何よりも大切なのは、いただいたお布施をきちんと寺院の維持・運営のために使うことです。
ここで一つ、注意しなければならないことがあります。
お布施を受け取っても帳簿に記録せず、金額も曖昧なまま――そんな状態では「気分経営」と言われてしまっても仕方ありません。
僧侶としての姿勢も、お寺の信頼も、こうした「見えない管理」から問われてくる時代です。
だからこそ、心あるお気持ちを、形としてしっかり記録することも現代の寺院経営には求められています。
※YouTube更新しました!
『5月8日発売ドリームジャンボ最強購入日』
①HPコラム/人間関係とお金に関する悩み(丸儲け住職YouTube)
②Facebook一般投稿 寺院運営を中心とした経営の話
③Facebook成功する寺院運営(オンライン会員限定)
天明寺の実践的な内容と具体例、ベンモウの考え
④X(ツイッター)毎日の名言・丸儲け住職YouTube内容のまとめ
⑤インスタ 人間関係とお金に関する悩み発信
⑥note 現代のお寺事情