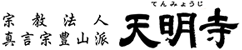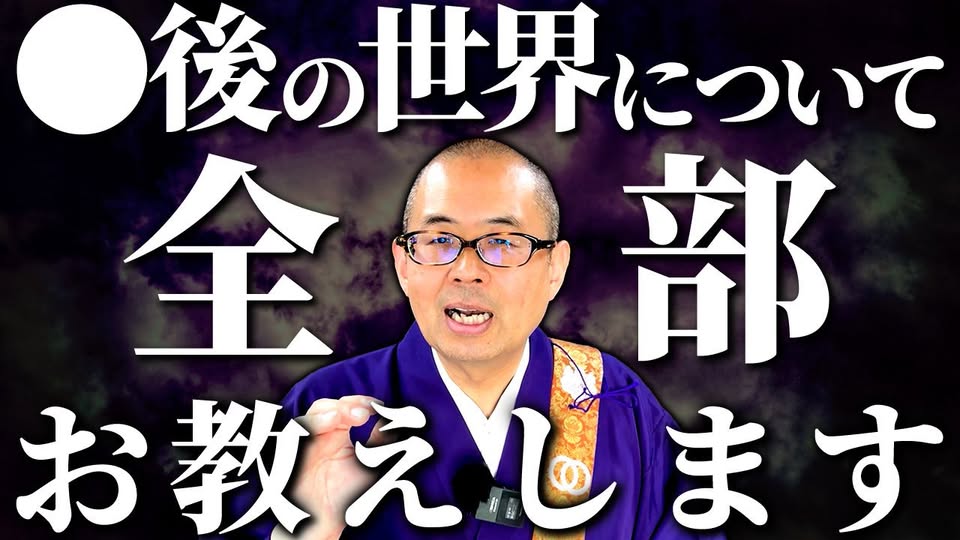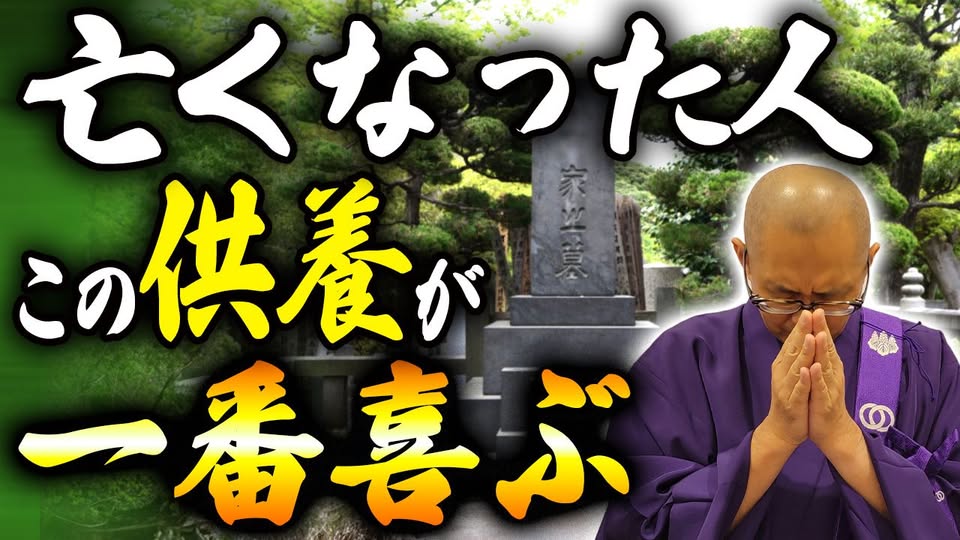2025/07/03お寺の「人件費」ってどれくらいが普通?〜労働分配率のお話〜
「労働分配率」って聞いたことありますか?
これは簡単に言うと、「利益のうち、どれだけ人件費に使ってるか」っていう割合のことです。
たとえば、製造業なら50%くらい、サービス業だと60〜70%くらいが目安と言われてます。
つまり、稼いだ分の半分とか、3分の2くらいを人件費にまわしてる感じですね。
じゃあ、お寺はどうなんだろう?って考えてみると……
実は、けっこう難しいんです。
お寺って、よくある会社とは違って、ほとんどが“個人事業”的なかたちで運営されています。
住職自身がすべてを担っているので、「自分に払うお給料」がそのまま人件費になるような感じです。
でも当然、収入が全部自由に使えるわけじゃありません。
仕入れがないように見えて、実はお香や仏具、法衣、塔婆や位牌、護摩札なんかも全部「仕入れ品」。ちゃんと経費がかかってるんです。
で、その経費を引いたあとに、全部をお給料として使っちゃうとどうなるか?
はい、余剰金(いわゆる利益のストック)がゼロになります。
これだと、急な修繕や予想外の出費に対応できなくなってしまいます。
だからこそ、「労働分配率をどれだけ抑えられるか」が、お寺の未来にとってすごく大事なんです。
もちろん、数字を下げればいいって話でもありません。
そこはもう、住職の考え方や覚悟次第。
でも、できるだけ「余剰金」を残すことができれば、将来的にお寺の運営もラクになりますし、いざというときにも安心です。
お寺経営って、意外とリアルなお金の話が多いんですよね。
でも、こういう話こそしっかり考えておかないと、“信仰”を支える体力がなくなってしまいます。
というわけで、今日はちょっとマニアックな「労働分配率」のお話でした。
※YouTube更新しました!
『トイレの掃除方法が運気を左右する!トイレの掃除すべきポイントについて解説』
①HPコラム/人間関係とお金に関する悩み(丸儲け住職YouTube)
②Facebook一般投稿 寺院運営を中心とした経営の話
③Facebook成功する寺院運営(オンライン会員限定)
天明寺の実践的な内容と具体例、ベンモウの考え
④X(ツイッター)毎日の名言・丸儲け住職YouTube内容のまとめ
⑤インスタ 人間関係とお金に関する悩み発信
⑥note 現代のお寺事情