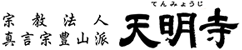-
2025.04.30
坊さんの理想と住職の現実
僧侶として生きるだけであれば、必ずしも住職になる必要はありません。
しかし、住職になるということは、そのお寺をどう存続させていくか、あるいは継承、または最終的な解体まで含めて責任を負うことを意味します。
「檀家もいらない、信者もいなくてよい。坊さんとしてただ生きていくだけでいい」
しかし、そのための情報発信は、自己満足に過ぎなくなってしまいます。
「お寺の住職として、檀信徒に何を示し、檀信徒には何をしてもらいたいのか?」
この問いを目的として据えたとき、初めて情報発信の意図が明確になるのです。
お布施の多少にかかわらず、住職として正しい行いを積み重ね、檀信徒を導き続けていくこと。
そしてその結果として、お寺の運営が成り立っていく。
これは理想的な姿です。
しかし、この理想を求めていく中で、現実に突きつけられる運営上の課題は重くのしかかってきます。
それでも、私たちは理想を求めるのです。
極端な言い方をすれば、適度に収入があり、適度に休みがあり、適度な運営ができれば十分だと感じる方もいらっしゃるでしょう。
けれども、現代においては、その“適度な運営”だけでは、お寺を長く存続させていくことは困難になっています。
お寺を残したいという思いがあるのならば、今こそ運営の在り方を見直す必要があります。
「それでも潰れても構わない」と考えるのであれば、それも一つの選択です。
しかし、それは、理想を語る余裕すらなくなるほど、生活が圧迫される未来を意味していることを、認識しておかねばなりません。
檀信徒のお布施に頼らない寺院運営を実現するには、経済的な安定と生活の保障という土台が不可欠です。
その意味では、お寺以外の収益を得る仕事に携わることも一つの選択肢かもしれません。
こうした背景の中で、寺院の存続と将来を担う後継者不足という課題も、さらに重みを増していくことでしょう。
※YouTube更新しました!
『5月に買いたい開運観葉植物10選』
①HPコラム/人間関係とお金に関する悩み(丸儲け住職YouTube)
②Facebook一般投稿 寺院運営を中心とした経営の話
③Facebook成功する寺院運営(オンライン会員限定)
天明寺の実践的な内容と具体例、ベンモウの考え
④X(ツイッター)毎日の名言・丸儲け住職YouTube内容のまとめ
⑤インスタ 人間関係とお金に関する悩み発信
⑥note 現代のお寺事情